こんにちは、みみみ!です。
学生時代には電車を利用していたのもあり、それなりに読書をする時間があったのですが社会人になってめっきりご無沙汰になっていました。
最近、引っ越しを機に自動車→電車通勤になったので、久々に読書を再開しています。(近所の図書館も嬉しいことに意外と充実している!!)
せっかくですし記録に残しておくために不定期で記事を作ることにしました。
「あれ?この本読んだことあるような…」みたいな悲しいこともなくなりますし笑
一次元の挿し木
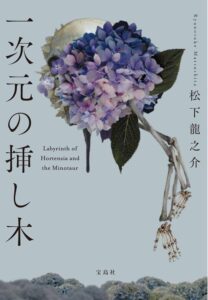
- タイトル:一次元の挿し木
- 著者:松下 龍之介
- 2025年第23回『このミステリーがすごい!』大賞・文庫グランプリ受賞作
書店で平積みされていて、あらすじに惹かれて購入。
あらすじ
ヒマラヤ山中で発掘された二百年前の人骨。大学院で遺伝人類学を学ぶ悠がDNA鑑定にかけると、四年前に失踪した妹のものと一致した。不可解な鑑定結果から担当教授の石見崎に相談しようとするも、石見崎は何者かに殺害される。古人骨を発掘した調査員も襲われ、研究室からは古人骨が盗まれた。悠は妹の生死と、古人骨のDNAの真相を突き止めるべく動き出し、予測もつかない大きな企みに巻き込まれていく――。
(宝島社HPより)
感想
初めて読む作家さんなので、期待半分不安半分で読み進めました。
まず内容は読みやすく、がっつり没入するというよりはさっくり読める感じ。
あらすじを見て『どんな話なのかな?』とワクワクしていましたが、所謂オチはかなり序盤で分かってしまいました。多くの人がそうなのでは?
個人的にはリアルと創作がもっとはっきり分かれていた方が好み。不可思議な存在があってもいいけれど、変に理屈をつけるくらいなら『そういう世界だ』と言い切ってくれた方が潔いと感じます。
とは言いつつ、普通に面白かったと思います。著者の方もまだまだ若い方なので新刊が出たらまたチェックしてみようと思います。
以下、ネタバレありのためご注意ください。
あらすじを読むと不思議なDNAの話ですが、要は妹はクローンでした、というオチ。
本編が始まる前の石御崎教授や父親たちの前日譚で分かってしまいましたが、あそこはもう少し後ろに載せる形ではいけなかったのでしょうか。折角の謎があまりにも気が付きやすくて(笑)
むしろ『あらすじで気が付けるだろ!』って感じかもですが…。
好きだったシーンは、紫陽花の株分けのくだりで、妹:紫陽(しはる)が『私と同じ』というところ。何だかお洒落で素敵だな~と思いました。植物でクローンの話だとソメイヨシノが有名ですしね。
読んでいて気になった点は大きく2つ。
ひとつ目は『ご都合主義』展開がちょっと多いこと。
・友江(父親たちの共犯者の研究者の義理の娘)が『義理の母が気に食わない』という理由で初対面の主人公に協力してしまう(そうはならんやろ~)
・今まで数々の関係者を『消して』きた牛尾が主人公にはあっさり倒されてしまう
・牛尾の犯罪は全然捜査されない?(石御崎教授や警察官も行方不明扱いすればギリギリ納得できるかも)
・紫陽の劇的復活。それまでの治療は効果なかったのに急に動けるようになるのは…。
ふたつ目は『あえて書かなくても良い描写』があったこと。
・石御崎教授のお葬式で『娘さんいないわね~』の世間話。からの唯(自称)の登場。
そもそも葬式(しかも殺人事件の被害者!)でそんな会話しないし、『わざわざこんな描写いれるってことは唯(自称)は真理(娘)で確定。ってことは真理(他称)は紫陽か。』って読めてしまいます。
無理に描写しなければ可能性の1つだったのに。。。
全体の話としては王道のストーリーで悪くなかったですが、こういう細かいところでたまに引っかかる感じでした。また、『謎/ミステリ』を期待して読むとちょっとがっかりするかもしれません。
汝、星のごとく
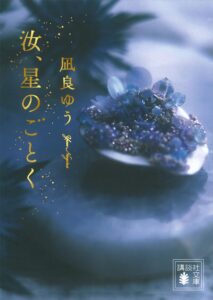
- タイトル:汝、星のごとく
- 著者:凪良ゆう
- 2023年本屋大賞受賞作
凪良ゆうさんの物語は、私のような『世間一般』に馴染めない感覚がある人にとって非常に優しく、救いのある話が多いです。図書館で予約してようやく(1年以上待ったかも?)借りることができました。
あらすじ
その愛は、あまりにも切ない。
正しさに縛られ、愛に呪われ、それでもわたしたちは生きていく。
本屋大賞受賞作『流浪の月』著者の、心の奥深くに響く最高傑作。ーーわたしは愛する男のために人生を誤りたい。
風光明媚な瀬戸内の島に育った高校生の暁海(あきみ)と、自由奔放な母の恋愛に振り回され島に転校してきた櫂(かい)。
ともに心に孤独と欠落を抱えた二人は、惹かれ合い、すれ違い、そして成長していく。
生きることの自由さと不自由さを描き続けてきた著者が紡ぐ、ひとつではない愛の物語。ーーまともな人間なんてものは幻想だ。俺たちは自らを生きるしかない。
(講談社HPより)
感想
ミスりました。先に『星を編む』(続編)を読んでしまっていました…。
なので既に北原先生の過去や、その後のふたりのことも知っている状態でした。ただ、ストーリー的にはそこまで影響がなかったのが救いでしょうか。(この本も結末をハラハラしながら読む感じではないし)
印象的だった言葉は
悩みのすべてを切り捨てられる最後の砦としての正論が必要なんです。
正論って守らなきゃいけないものでも、他者に押し付けるものでもなく、こういう風に上手に使えたら良いですよね。もう一つ、
「もしくは、選びなさい。」
捨てる。選ぶ。
意味はちがうのに限りなく近いふたつの言葉。
何かを捨てないのは、何も選ばないのと同じって良く言われることですが、
自分で選んできた北原先生の言葉には説得力がありました。ここは『星を編む』を先に読んでいたからこそ刺さったのかもしれません。
以下、ネタバレありのためご注意ください。
家庭の事情で道を選べなかったが、最後には櫂と共にいることを選んだ暁海。
一度は夢を叶えたが、何もなくなった最期に暁海のもとへ帰ることを選べた櫂。
ふたりは多くをすれ違い、その結末も分かりやすいハッピーエンドではなかったけれど、それぞれがしっかりと『選んだ』ものだったからか、寂しさはあっても悲壮感は感じなかった。
高校時代のふたりはまだ子どもで、だからこそ思うままに恋愛をし、それがずっと続くことを疑っていなかった。
ただ、櫂が夢を叶えて上京してからは、櫂の当たり前に大きな変化が現れる。忙しさと引き換えにお金や華やかな生活に染まっていく。
一方で不倫され夫から捨てられた母を放っておけない暁海。田舎の島暮らし、血縁関係、そして金問題に翻弄される。
子どもから大人になり、世間のままならさの中で徐々にすれ違い、別々の道を歩むふたり。その後櫂は多くのものを失い、暁海は少しづつ積み上げて、最期にはふたりの道は交わる。
個人的には暁海を裏切って浮気していた櫂は「ダメな男だなあ」と思うのだけど、そういう理屈や『正論』を超えるものが愛だからしょうがないよねというのも分かる気がする。
暁海にとってのターニングポイントをもたらしてくれる、北原先生はこの本だけだと背景が謎すぎて人物像が見えないかもしれないので是非続編である『星を編む』も読んで欲しい。
また、作中に『夕月(ゆうづつ):宵の明星』『赤星:明けの明星』(両方とも金星のこと)がキーワードとして出てくる。ふたりの繋がりとしての意味合いや金星の二面性を表現していると思われる。タイトルの『星』も然り。
凪良ゆうさんの作品は『流浪の月』や他の作品もだけど、【そういう幸せがあってもいいよね】というかたちを優しく表現してくれている、そこが多くの人に共感される所以かと思う。
幸せや愛のかたちは人それぞれ、あなたや世間と違う私も、自分なりの幸せを選んでも良いと悩んでいる人も勇気を貰えるような。
これからもそういった物語を作っていって欲しいです。
最後に北原先生のお言葉をもうひとつ。
「ぼくは過去に間違えましたが、『つい間違えた』わけではありません。間違えようと思って間違えたんです。後悔していませんが、そんな間違いは一度で充分だとも思っています」
私もいつか何か『間違い』を選ばなければならなくなったとき、しっかりと間違えられるような大人になりたいな。


