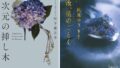こんにちは、みみみ!です。
2025年の7月に読んだ本の紹介です。
今月はお気に入りになりそうな新しい作家さんを見つけてほくほくしています。
それではどうぞ。
スターゲイザー

- タイトル:スターゲイザー
- 著者:佐原 ひかり
表紙が好みだったので、所謂ジャケ買い。結果としては大当たりでした!
あらすじ
コバルト短編小説新人賞&氷室冴子青春文学賞出身の著者が贈る、
令和の青春×アイドル文学が、今ここに生まれる!アイドル事務所「ユニバース」に所属するデビュー前の青年、通称「リトル」。
彼らはデビューに向けて、限られた時間の多くを費やしレッスンに励んでいた。
そんなある日、リトルたちが出演するイベント「サマーマジック」で最も活躍した一人を、デビュー間近のグループ「LAST OZ」に加えるという噂が流れだす。
この噂をきっかけに皆が熱を帯びていく中、リトルの一人である加地透は疑問を抱いていた。
“恋心も、学校生活も、自分の体も、全てを捧げなければデビューは叶わないのか?”デビューに対して人一倍強い野心を抱いている持田、
わずか14歳にしてソロデビューを打診された遥歌、
誰よりもストイックで自分の見え方を計算し尽くした振る舞いをする葵、
芸能人一家の複雑な環境で育った問題児の蓮司、
デビューができる期限まで残り一年を切った若林、そして透。デビューを目指すこと以外はすべてバラバラの6人が出会った時、
彼らの未来は大きく変わる――かもしれない。(集英社HPより)
感想
あまり期待をせずに読み始めたのですが、非常に好みな小説でした。
私、色んな人物の視点で描かれる群像劇が好きなのですが、この小説も各章でそれぞれアイドルの卵の一人に焦点を当てて描かれています。
目指すところや得意なこと、苦手なことがそれぞれ異なるメンバー同士の縁が最終的に繋がっていくところなんかが非常に良きでした。個性もはっきりしていて、実際のグループいそう!な感じ。
ちょっと読むつもりが一気読みしてしまうくらい面白かったので、この著者の方の他の本も読んでみようと思います。
以下、ネタバレありのためご注意ください。
(ちょっと作中のキャラクターに感情移入しすぎて書き出したものをつらつら書いているので、文体がポエムっぽいのはご了承ください。)
加地透の視点から物語は始まる。彼は無自覚な”天才”で、だけど”完璧”ではなくて、どうにも理解されにくい。
きっと誰よりも優しい気持ちを持っているのに、それを持て余してしまっている。そしてそれ故に大切な存在だった大地はアイドルの道から離れてしまう。
持田良はルッキズムに苦しむ。アイドルだから仕方ない反面、中々ぐさっと刺さるものがある。身内にすら”推して”貰えないと知ったときの悔しさや絶望はいかほどだろう。
歌やダンス、ファンサというアイドルとしての技術より手前のスタートラインで切られてしまう。だけど諦めきれない、ある意味一番共感できた存在だった。
和田遥歌の苦しみを私は分かってあげきれない。見た目ってやっぱり大事な部分だと思うから。
だけど、遥歌は実はとっても苛烈な精神を持っていて強か。天使のような身体を傷つけてでも蓮司をアイドルの世界に引き留めてみせた。そんなギャップも彼の魅力を増していると思う。
三苫葵は私のありたい姿を体現している。アイドルとしてお金をもらう以上、プロとして自分を律する。当たり前のようでいて、中々難しい。
元々”完成”しているかに見えた葵も物語の中で成長していく。鏡に映る自分だけでなく、周囲を知って世界を広げていく。葵の章から6人の話が新しいステージへと進んでいく。
真田蓮司は正直だと思う。自身のやりたいこと、好きなことがしっかり分かっているから、彼はまっすぐで、だからこそ周囲とも軋轢を生む。
アイドルとしての人生に頓着がない蓮司が遥歌からアイドルとして求められたとき、きっと彼にはその気持ちが分かったのだろう。願いというにはドロッとした想いだとしても。結果として蓮司も役者には興味がない若様を引き留める道を選んだ。
若林優人は最年長だけど、一番幼い印象を受けた。働かずにお金をせびってくる父親のせいで、色々なことを我慢して飲み込んできたから心が縮こまってしまっているような。
そんな彼もn.overの活動を通してちょっとずつ心がほどけていくようだったのが嬉しい。そして最後のステージで光を浴びた彼らの姿を見て、本を閉じたあとも涙が止まらなった。
最後に、タイトルの『スターゲイザー』の意味について。私は、『正式なアイドルデビューという星を見つめるアイドルの卵』や『ファンがアイドルという星に釘付け』という理解をしていましたが、インタビューで著者の方が↓のように語られていました。
この小説のタイトルは『スターゲイザー』、星を見る(gaze=凝視する)人という意味です。そこにはファンが「スター」であるアイドルを見るという視線もあるし、コンサートでサイリウムを揺らす客席の星空っぽさに象徴される、アイドルから見たファンという視線もあります。それともう一つ、アイドルから見たアイドルという視線も重ね合わせているんです。本人は気づいてないんだけれども、すごく光っている部分を仲間がゲイズすることで、その人が変わっていく……そんな話にもなっているのかなと思います。
集英社 青春と読書より
鳥と港
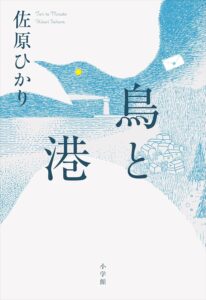
- タイトル:鳥と港
- 著者:佐原 ひかり
あらすじ
大学院を卒業後、新卒で入社した会社を春指みなとは9ヶ月で辞めた。
所属していた総務二課は、社員の意識向上と企業風土の改善を標榜していたが、
朝礼で発表された社員の「気づき」を文字に起こし、社員の意識調査のアンケートを「正の字」で集計するという日々の仕事は、
不要で無意味に感じられた。
部署の飲み会、上司への気遣い、上辺だけの人間関係──あらゆることに限界が来たとき、
職場のトイレから出られなくなったのだ。
退職からひと月経っても次の仕事を探せないでいる中、みなとは立ち寄った公園の草むらに埋もれた郵便箱を見つける。
中には、手紙が1通入っていた。
「この手紙を手に取った人へ」──その手紙に返事を書いたことがきっかけで、
みなとと高校2年生の森本飛鳥の「郵便箱」を介した文通が始まった。
無職のみなとと不登校の飛鳥。それぞれの事情を話しながら「文通」を「仕事」にすることを考えついたふたりは、
クラウドファンディングに挑戦する。
『ブラザーズ・ブラジャー』『人間みたいに生きている』の新鋭が描く〝これから〟の働きかたの物語!小学館HPより
感想
前述の『スターゲイザー』が好みだったので、読んでみました。
ちょうど自分が推し活の中で手紙というものに興味を持ち始めていたこともあり、タイムリーなテーマでした。
個人的には”これからの働きかたの物語”というアオリはちょっと首をかしげてしまうし、ストーリー的には少し引っかかるところもありました。
特に主人公みなとが良く言えば純真、悪く言うと将来への想像力が欠如しているように見えてしまうことが残念でした。文通(特定個人へのことば)を仕事、ビジネス(大衆均一化)にする課題って最初に考えませんかね?
ただ、それを補って余りある、手紙、ひいては『想いをことばに残す』ことの尊さを私は感じました。ので、これもオススメの一冊です。
以下、ネタバレありのためご注意ください。
ストーリーというよりは印象に残ったフレーズを紹介します。
便箋、インク、封筒、切手、気持ち、話題、ことば。すみずみまでこだわって、整理して。手紙を書くときに覚えるのは、心の手入れをしているような感覚だ
これは手紙を書いたことがある人ならば、非常に共感できるのはないかと思います。
手紙を書くとき、内容だけでなく沢山のことを考えます。便箋や封筒、シーリングのデザイン、どんなペンで書くか、じっくり書くかさらっと書くか。改行の位置は?無駄な言葉はないか?フレーズが重なっていないか?この言い回しはあっていた?そもそも自分の本当の気持ちは?
手紙は相手に対して出すものではあるけれど、その過程で自分とじっくりと向き合うものでもあると私も感じます。不思議なことに相手が大切であればあるほど、丁寧に自分をお手入れできるみたいです。
今ここにいない人にも、そのとき感じたこととか気持ちを知ってほしい。言葉にして書き残しておきたい。から筆を執る。ってことだよね、たぶん。だから私も、この手紙に今の私の心をぎゅうぎゅうに詰めて贈りたいと思います。
このフレーズで良いなあと感じたポイントはいくつかあって
まずは『”今”の私の心』というところ。自分の心ってずっと変わらないようでいて、やっぱり移ろいゆくもの。手紙って意外と”そのとき”のライブ感みたいなものもあるなあと考えていたので、刺さりました。
次は『ぎゅうぎゅう』。手紙って思っていたよりも文字数書けないんですよね。枚数が多すぎると迷惑かなあ、とか考えると、キツキツ…。それを『ぎゅうぎゅう』という可愛らしい表現にしてくれて、自分も使おうと思う素敵な言い方でした。
最後に『贈りたい』。送る、ではなく贈る。ただ、動かす/移動させるのではなく、気持ちのこもった大切なものを与える。こういった”ことばを丁寧に考える”のも手紙の醍醐味ですよね。
手紙を書く。ことばにして、書きとめて、記憶や感情を相手に預けておく。そうすれば、こうやって、ふとした何気ない瞬間に手元に戻ってくることもある。
先ほどのライブ感ではないですが、意外と自分のことって忘れがちになることもあると思います。一方で贈られたことばは自分の中で根付いていくこともあります。
忘れかけていた自分や、「そんなこと言ったっけ?」みたいなことも日記を読み返していくと出会えたりもします。それが誰か自分以外の人からだったらとっても嬉しくなれそうです。(自分は残念ながらまだ経験ありませんが・・・)
というわけで、手紙やことばをより考えるきっかけとなる、良い一冊だと思いました。きっとこの本を読んだら、誰かに手紙を書いてみたくなるはず!笑
人間みたいに生きている

- タイトル:鳥と港
- 著者:佐原 ひかり
あらすじ
食べることそのものに嫌悪を覚えている女子高生・三橋唯。「食べること」と「人のつながり」はあまりに分かちがたく、孤独に自分を否定するしかなかった唯が初めて居場所を見つけたのは、食べ物の匂いがしない「吸血鬼の館」だった──。
朝日新聞出版HPより
感想
佐原ひかりさんの著書、3冊目。
あらすじを読まずにタイトルだけ見て図書館で借りました。私は自分のことを社会不適合者とまではいかなくても、あまり生きるのが上手でないと思っているので、共感できるかな~?とか思っていました。
なのですが、あらすじの通りもうちょっと物理的(原因は精神的なものだとしても)な『食事』がテーマになっていて少しびっくりしました。
食べることが大大大好きな私としては共感にしくかったり、主人公が女子高生のため(?)少し独善的に見える描写もあり、3冊の中ではイマイチかなという評価です。
読み物としては普通に面白いですが、少しティーン向けかな?
以下、ネタバレありのためご注意ください。
本作は簡単にまとめると、『食べる』という行為に嫌悪感を覚えてしまうようになった主人公:三橋唯が『吸血鬼の館』に住む泉さんと出会い、最終的には自分と向き合うようになる話です。
口は穴だ。顔に空いた穴。備え付けの歯と舌を駐使し、自分に自分以外の何かを取り入れるための穴。今日も無数の死骸をここに入れ、ねぶり、砕き、噛みちぎり、飲み込んだ。
なるほど。食事という行為に対して嫌悪感をもって描写するとこういう風になるのか・・・と冒頭からちょっと引いてしまいました。でも確かに「ダイエットしたい!」とかの共感されやすい気持ちに対して、描かれているこの感覚を誰かに分かってもらうのは難しいかもしれません。
「感覚的に」食事ができない唯に対して、「物理的に」食事ができない泉さんが登場しますが、私的にはこの泉さんが消化不良というか・・・。ミステリアスな設定だけ使われているような、そんな感じがしてしましました。
一番共感できたのは、食事をできるようになるためのセミナーで唯と出会った人(名前忘れました)が言っていた、
不便だからどうにかしたい。飲み会も接待も結婚式もコース料理まみれだ。誰かと食えないってのは社会生活に支障をきたしすぎる。
というところ。分かる。私は多人数でコミュニケーションをとるのがあまり得意ではないのですが、普通に不便なんですよね。「自分を変えたい」とか高尚な考えはなく、ただただ社会生活を円滑に過ごせないのが困るというか…。
タイトルの意味は実はこのことなのかもしれません。誰しもきっと大なり小なり苦手なことを抱えながら、不便だなと思いながら、それでも『人間らしく』振舞っているだけなんだと。そうやって少しでも自分を許せるようになれば良いのかな、なんて思いました。